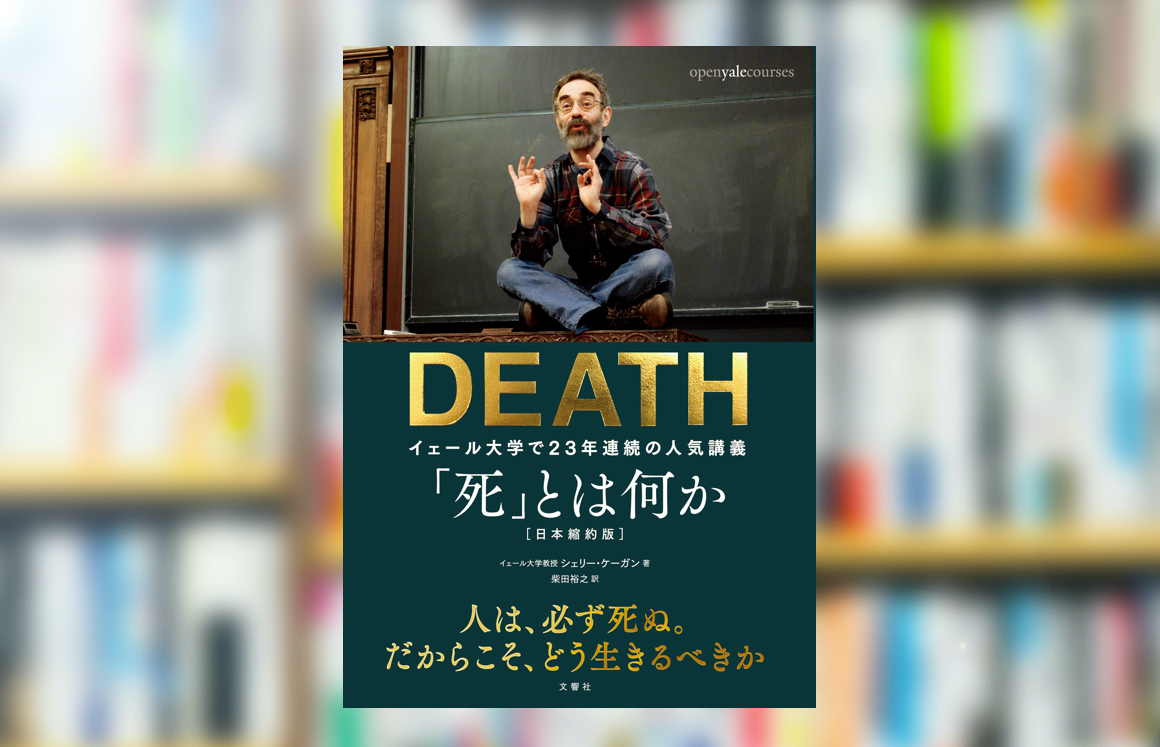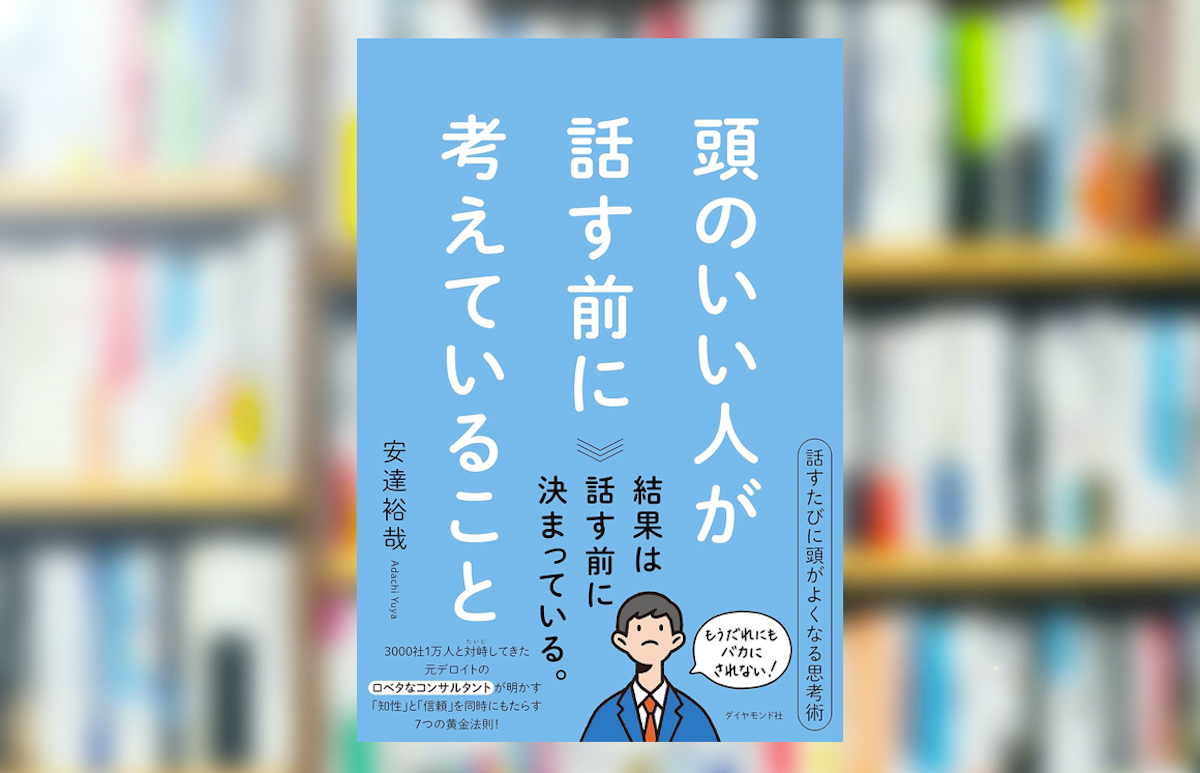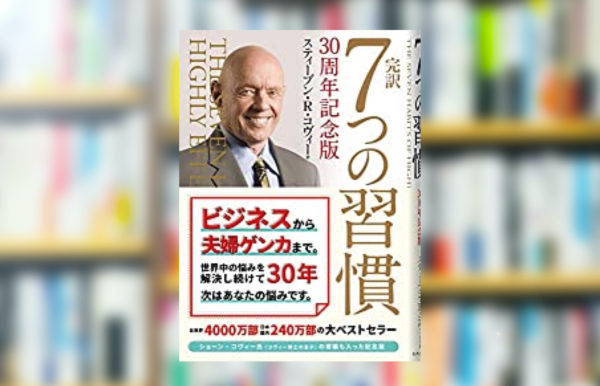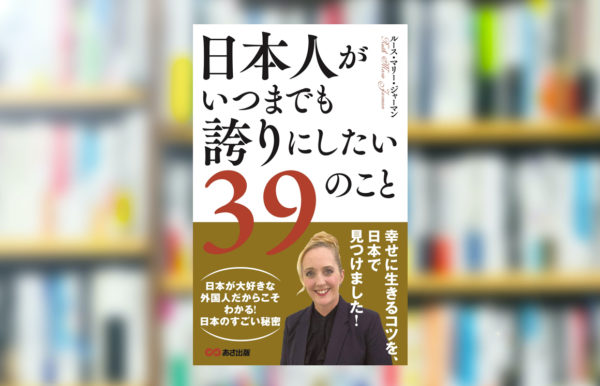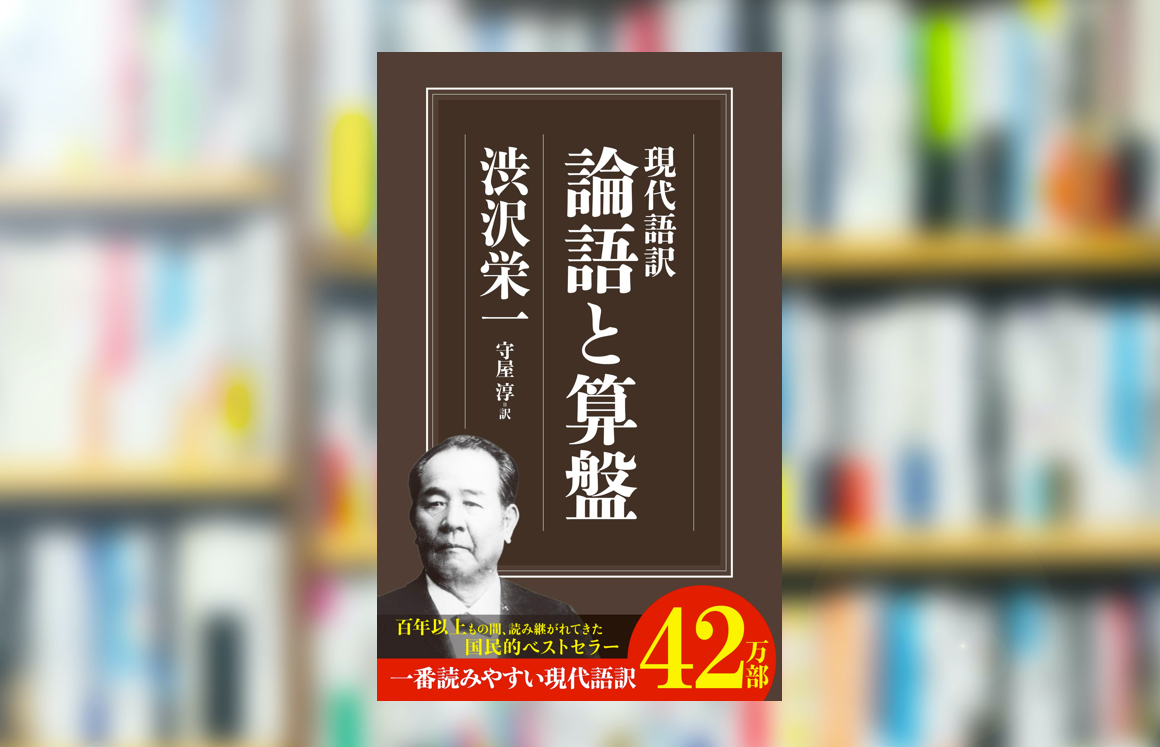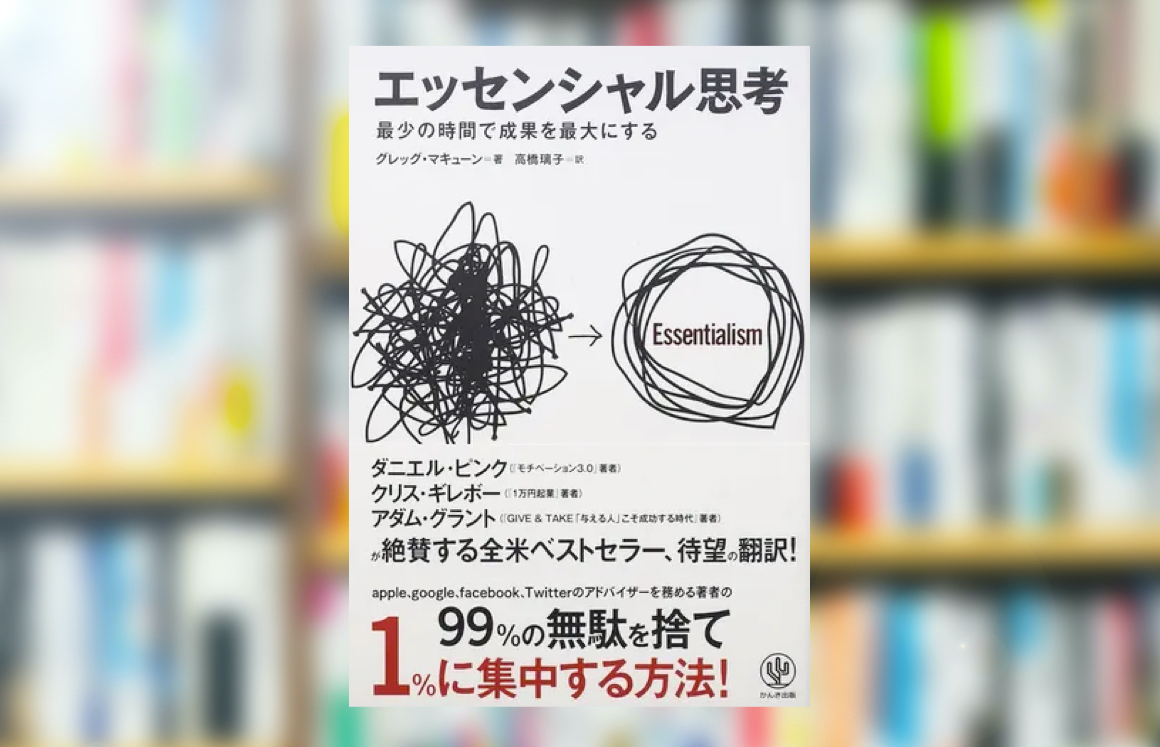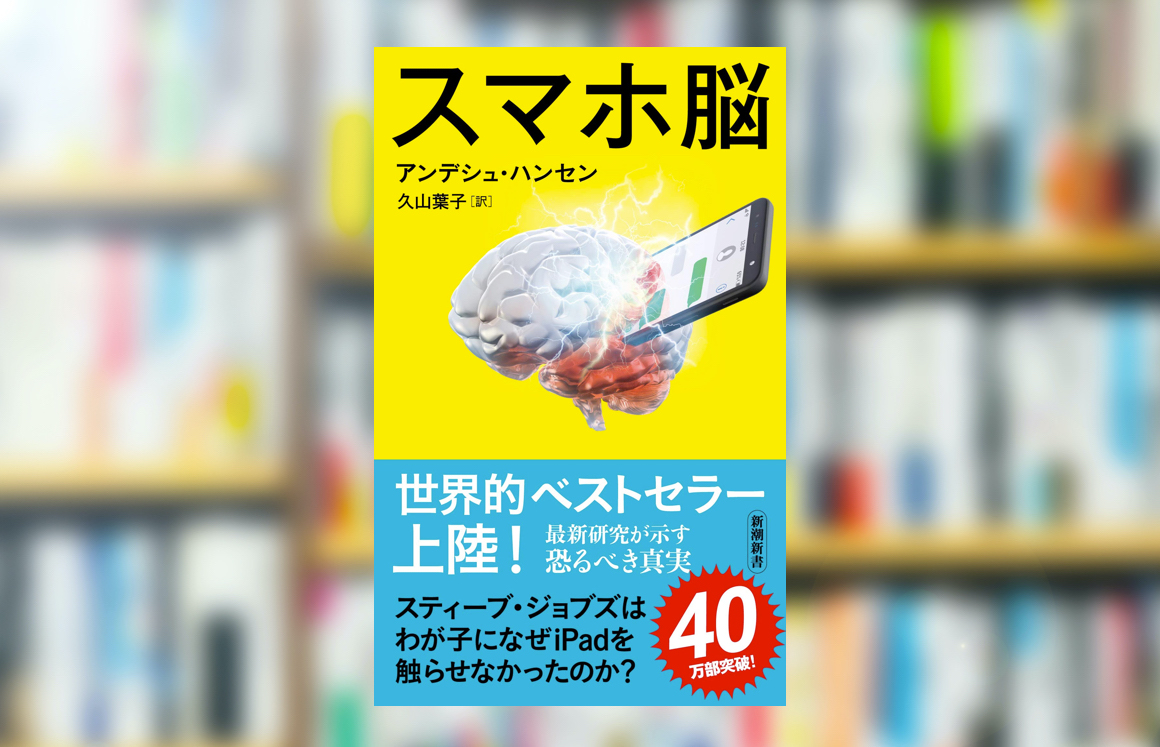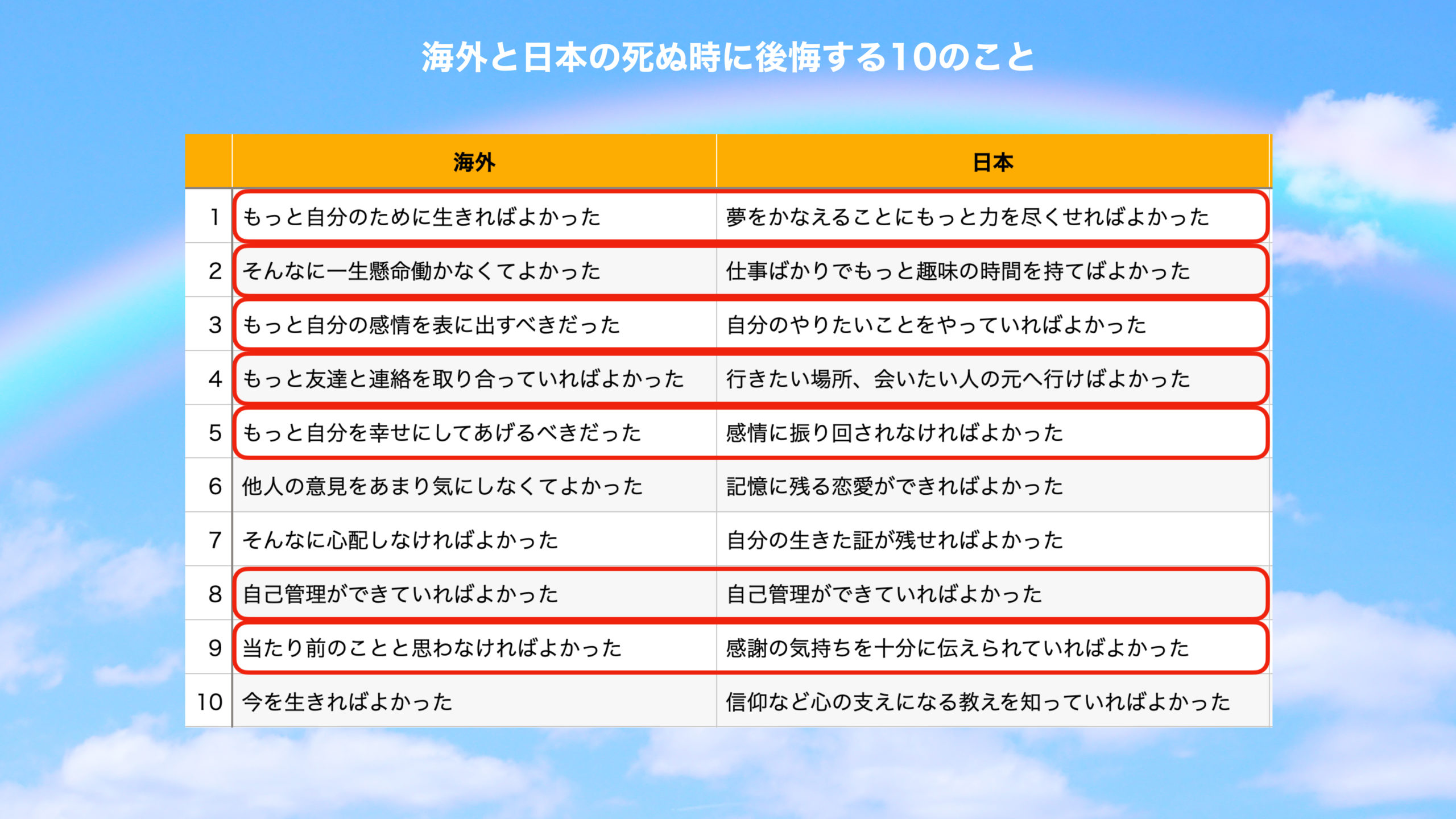いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか

書籍「いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか」で学べる一番大事なことは、一言でいうと以下の1文です。
いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか
- 人間とはなんだろう?
- 死とはなんだろう?
- 人はなぜ生きるのか?
- 人はどう生きるのか?
- 考える技術
- いまを生きる人たちへ
はじめに
本書を開くと、まず「解説 立花 隆という人」という題で、テレビ番組などでもよく知られるジャーナリストの池上彰さんが立花隆さんという人について解説してくれています。
立花隆さんは、「知の巨人」という呼ばれ方をしていますが、とにかく知識量といい、思索の力といい、興味関心の幅といい、群を抜いていたといいます。
同じジャーナリストという立場で、文系や理系などの垣根を越え、学問の融合という観点から時代の最先端の科学に目を配り、取材を続けました。その原動力となっているのは正義感でもなく、好奇心からだということです。
本書からは、私たちにとって、生きること、学ぶことの好奇心を伝えられればという意思が感じられればよいのではないでしょうか。
いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか
人間とはなんだろう?
人間は関係性のなかにあり、<私以外の人間すべて>と<私>との関係性を考えなければなりません。
それはフィジカルでもメンタルでも多様性について知れということです。
子供が大人になるということは、実は、他人というものは、自分とメンタルに全く異なった存在で、ものの見方、考え方、感じ方がすべてちがうのだということを知ることなのです。
ギリシャの哲学者アリストテレスは、「人間は生まれながらにして知ることを欲している」と言いました。食欲や性欲と同様に、種族維持のための本能に基づいた欲求だといえます。
これは他の動物にはできないことで、自由な思考ができるのは人間だけです。
つまり、集団で知能を合わせて何かをつくるとか、新しい社会を作り出せるのは人間だけだといえます。
その中で、人間はなにを知りたいのかというと、最も知りたいものに二つのものがあるといいます。
一つには自分自身についてです。そしてもう一つは自分以外の世界についてです。
後者については、自然科学によってかなり解明されているものの、前者の自分自身とは何かという問いについては自然科学の達したレベルにはまだまだ達していない状況にあります。
では、その自分自身の存在と非存在をわけるものとは何なのでしょう。
人間の個別の存在は、本人の記憶に支えられて存在しているとともに、他者の記憶に支えられて存在しています。もし自分の存在が、世界のありとあらゆる人の記憶の中から突然忽然と消え失せてしまったとしたら、本人は意識の中でまだ存在しているつもりかもしれませんが、社会的にはもう存在していない人間の部類になってしまいます。
死とはなんだろう?
「死」という問題は、一つのことだけを専門的に調べても足りず、学ばなくてはいけないことが多すぎるといいます。
そして、少なくとも人間は死を避けることができません。
立花さんは、「死は怖くない」という心境に到達したのは、番組の取材を通じて臨死体験に関する知識を得たからという理由以上に、年を取ることによって死が近しいものになってきたという事実があるといいます。
死はどうして怖いのか?
たいていの人は、ただ本能的に死を恐れているだけで、実際は、自分の存在がこの世から消えてしまうことに対する恐怖、死のプロセスについての恐怖(苦痛など)、死後の世界に対する恐怖(裁かれる、罰される可能性など)にわかれるだろうということです。
なお、イエール大学教授の道徳哲学・規範倫理学の専門としているシェリー・ケーガンの著書『「死」とは何か』では、死の恐怖を剥奪と喪失と表現しています。
これは、自分の存在がこの世から消えてしまうことに対する恐怖に当てはまるかもしれません。
詳しくは以下の記事で紹介しています。
そして、誰もその死のことを知らないからこそ恐怖を持ちます。
誰でも人生の成長過程で、「初体験」を経験せざるを得ないが、その度先人の知識を得ることができる。
しかし、死に関しては、死の向こう側に行った人の知識を得ることができない。
だからこそ死は永遠の謎であり、知らないことに対する恐怖ともいえる。
では死を持って最後に残るものはなにか?という問いにスイスの心理学者ユングの見解があります。
人は死ぬとき、この世に属する一切のものを捨てていく。
それは物質的存在だけではなく、この世に属する思いの一切が捨てられ、欲望や我執の一切が、希望さえ含んで消えていく。
最後の最後にギリギリ残るものは何なのか。
これこそが私、といえるものは何なのか。
それは私のまわりで起きたできごとの総体であり、私自身の歴史であり、私の成就したものの総体であるとユングはいいます。
そして立花さんは、この問いに対して、絶対的に正しいというような答えが出るわけがない。
将来に身を持って知ることができるのだから、お楽しみとしてとっておき、生きている間はよりよく生きるかにエネルギーを使った方が利口だと思うようになったということです。
人はなぜ生きるのか?
ギリシャの哲学者エピクロスは、人生の最大の目的とはアタラクシア(心の平安)を得ることだと言いました。
結局、死ぬというのは夢の世界に入っていくのに近い体験なのだから、いい夢を見ようという気持ちで人間は死んでいけるんじゃないかという気持ちになったといいます。
人はなぜ生きるのかという問いに対して答えはありません。
立花さんは「生とは何であり、死とは何であるのか」は、人が生涯追いかけざるをえない難問であり、答えは年齢によってかなり、あるいは微妙に変わってくるといいます。
還暦以前はどこか生きることにガツガツして、毎日歴史の新しいページが目の前でめくられてるのをその場でウォッチしているような気がして、生き続けることが嬉しかった。しかし、還暦をすぎてみると、目の前で起きていることは、どことなく映画を二度見しているような感覚に何度も襲われてしまうということです。
立花さん自身は、患った病気において、延命治療よりQOL(クオリティ・オブ・ライフ)として生活や人生の質を維持することを望みました。それは少しでも長生きしたいというより、少しでも長く知的生産活動(本を書くという行為)をしたい。同時に良質の知的消費活動(良質の読書。頭をかなり使わないと読めない本を読んで楽しむ。あるいは良質の芸術鑑賞活動をする)を維持したいという思いがあったからです。
結局、生きるのは生き続けることを求めて、死なないためとも言えるかもしれない。
そして目の前にある問題を解決し続けるということなんだと述べています。
人はどう生きるのか?
青春期は単に時間的に定義できるものではありません。
自分の生き方を模索している間が青春です。
精神だけが老化した青年とは、あらゆる失敗の可能性を前にして足がすくんでしまいチャレンジできなかった青年のことである。
あらゆる失敗の可能性を忘れている人は、逆に大胆に生きようと無謀に生きたというだけである。
あらゆる失敗の可能性を見すえつつ大胆に生きた人こそよく青春を生きたと言えるだろうと立花さんはいいます。
そして、大学に行く最大の目的は、自分の能力を発見して、自分の働き場所を見つけることにあります。
社会という人類全体の共同事業の一画に、自分なりの働き場所を発見して、働くことです。
その発見のためには、たくさんの試行錯誤を経験する必要があります。
立花さんは、自分の少年時代について、大人になったつもりの少年だったと振り返っています。
しかしそれでいいのだといいます。
したり顔で、大人になったと勘違いして、背伸びしているうちに、人間は本当の大人になっていきます。
無知で傲慢で不遜でいながら、それに気づかないでいられることが若者の特権だということです。
立花さんは、人生の価値は成り行きにあるといいます。
旅(人生とも言える)は結局のところ出会いなのである。出会いは本質的に計算になじまないことなのだから、予定なんて立てずに成り行きにまかせるのがいちばんであるということです。
そして、いろいろなことで考えすぎるとだいたい失敗します。
あとは脳に任せ、反射神経のおもむくままに行動すると、だいたい正解に当たると述べています。
一番大事なことは、自分の脳を育てるのは自分自身以外にないということです。人から与えられた正解に満足せず、自分の脳に何を体験させるのか、要するに自分の時間を使って何をやるかです。
人間なにが幸せかといえば、「やりたいことを、やりたいように、やる」という一点に尽きると思っているということです。
そのためには、集団の中では「勝ち組」「負け組」に分類しがちだが、勝ち負けで決まると思う人たちの人生ゲームからいち早く脱して、勝ち負けにわれ関せず、と思う人たちの側に身を移してしまうのが正しい戦略だということです。
考える技術
なぜ生きるのかを自分で見つけるためには、考える技術が重要です。
何か問題があって解を出すということも考えるということですが、ここでも唯一絶対の正解なんてあるのかと疑問を持つことです。二者択一で考えたり、最適な解があるはずだという考えを捨てることも大切なことです。
そして、その行為の前提にはインプットとアウトプットが必要になります。
まずはアウトプットの前にたくさんのインプットをすることだと立花さんはいいます。
特に思想については、若いうちにできるだけ沢山浴びておいた方がよいということです。
いろんな思想を味わってみるという経験をある程度積まないと、新しい思想に出会ったときに、それを正しく評価できないからです。
そしてインプットにおいて重要なのは読書だといいます。
立花さんは、一般教養のための読書について、読書の14カ条というものを掲げています。
各項目は実際はもっと長い文章になっているため、少し省略していますので、気になる方は本書を購入して読んでもらえればと思います。
- 金を惜しまず本を買え
- 一つのテーマについて類書を何冊か求めよ
- 選択の失敗を恐れるな
- 自分の水準に合わないものは無理して読むな
- 読みさしでやめようとしても、一応終わりまでページを繰ってみよ(意外な発見があるかも)
- 速読術を身につけよ
- 本を読みながらノートを取るな(その時間で5冊の類書を読める)
- 人の意見やブックガイドのたぐいに惑わされるな
- 注釈を読みとばすな
- 懐疑心を忘れるな(デタラメはいくらでもある)
- おや?と思う箇所に出会ったら、ソースや著者がそう書いた根拠を考えよ
- 何かに疑いを持ったら、オリジナル・データや生のファクトにぶちあたるまで疑いをおしすすめよ
- 翻訳は誤訳、悪訳がきわめて多いため疑ってみよ
- 若いときは何をさしおいても本を読む時間をつくれ
いまを生きる人たちへ
現代は変化の激しい時代です。
しかし人間は時代は逃れられません。
「自分という人間」と「自分が生きた時代」というものは不即不離の関係にあります。
その時代に起こることは現実として受け入れなければならないという心構えを持つことが大事です。
何があり得て何があり得ないかということは、事前には決して分かりません。
だからこそ、この世界を常にダイナミズムの相の下に捉えることが必要です。
「パンタ・レイ(万物は流転する)1」こそ、永遠の真理だと立花さんはいいます。
- 古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの思想。どんなものも時の流れに従い変わっていく、二度と同じものはないことをいう。 ↩︎
歴史やサイエンス、テクノロジーも現代は知的で実に面白いと立花さんはいいます。
そして、環境問題などにおいて、技術の抑制ではなく、科学も自然も味方につけた考え方で解決を望んでいます。
そして重要な武器として「情報力」を挙げています。
英語力やIT力に加えて、情報が正しい内容か、その情報を解釈する能力のことを情報力と表現しています。
特にプロでも、直感的にホントだろうと思った情報については、ウラ取りを忘れてしまいがちになるそうです。確認が得られないうちは、それが未確認情報であるということを忘れずに扱うことが大切です。
情報を正しく解釈して、どう行動しなければならないのかという、状況判断能力を身につける必要があります。
学校の勉強だけでは足りません。もっと広い範囲での学習が必要です。そのためにはいつもさまざまな情報を手に入れて、それぞれを比較して本質を見極める力をつける必要があります。
まとめ
本書の最後の項には、最後のお断りとしてこう書いています。
本に書いてあるからといって、何でもすぐに信用するな。自分の手にとって、自分で確かめるまで、人のいうことは信じるな。この本も含めて。
教授として学生への教育にも力を入れていた立花さんですので、若者へのメッセージも多く含まれた内容でした。
特に、情報力を高めて、読書や出会い、経験を重ねて様々な分野のインプットを広げ、いつ起こるかわからない困難や問題に対応できる力を身に着けてほしいという思いが伝わります。
そしてタイトルでもある「いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか」という問いに対しては、「人はなぜ生きるのか?」や「人はどう生きるのか?」の項で書かれていた晩年の言葉が表したと思います。
ギリシャの哲学者エピクロスの言葉、「人生の最大の目的とはアタラクシア(心の平安)を得ること」を受けて、いい夢を見るために気持ちよく死ぬ準備をしよう。そのために、「やりたいことを、やりたいように、やる」。更にそのためには、自分の脳を育てるのは自分自身以外にないのだから、自分の時間を大事にして、インプットとアウトプットを通じて、目の前のことをこなそうという思いが受け取れました。
【内容情報】
2021年に惜しくもこの世を去った知の巨人、立花隆。彼が科学から政治まで幅広いテーマを追った根底に、「人間はどこから来てどこへ行くのか」への興味があった。脳死、臨死体験、宇宙、生物学、歴史、戦争…。あらゆるテーマから浮かび上がる、人間と人生の意味をめぐる旅。この本はまさに、今を生きるすべての人へ贈る21世紀の『君たちはどう生きるか』だ。膨大な著述を凝縮した決定版がここに登場。【著者情報】
いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 内容紹介より
立花 隆(タチバナタカシ)
ジャーナリスト、作家。1940年長崎県生まれ。1964年東京大学文学部仏文科卒業後、文藝春秋新社入社。1966年退社し、翌年東京大学文学部哲学科に学士入学。在学中から文筆活動を始め、宇宙科学から生命科学、宗教から政治まで、幅広い執筆活動を続けた。東京大学や立教大学では教鞭も取った。2021年4月30日、急性冠症候群のため死去。享年80(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)